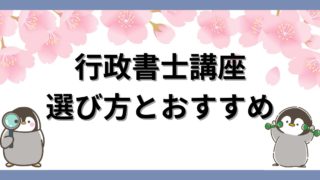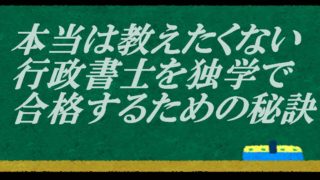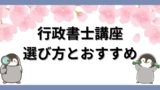講座を選ぶ上で最も重要な要素が合格実績。
行政書士試験の合格実績を18社を調査しました。
調査したまでは良いのですが、多くは合格実績をまともに公開していない。
とても知りたい数字なのに、ほとんど未公開。
とはいえ、わかること・推察できたことが多々あります。
講座選びの一つのヒントとして、合格実績について掘り下げていきます。

私が受験時代にとても知りたかったこと、「合格者の何%が講座利用者であるか?」。
納得できる回答は当時ありませんでした。
推定になりますが最後にお話しします。
注)一部公表できない、してはいけないデーターを含んでの話になっている部分があります。
はぐらかしている、明言、根拠のない話などはお察しください。
行政書士講座合格実績
まずは調査結果から
集計時期:2024年2月、2022年試験ベース。
2023年試験発表後ではあるが、各社結果は例年夏付近(現時点不明)。
基本情報:2022年度行政書士試験結果
合格率 :12.13%
合格者数:5.802人
| 社名 | 合格率(%) | 合格者数(名) | 合格体験記数(件) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アガルート | 🥇56.1 | 🥇296 | ※ | 2023年56.11% 303名 体験記未集計(多すぎのため) |
| フォーサイト | 54.1 | 前年までと集計方法が異なる | ||
| LEC | 48.8 | 53 | 合格率は模試の実績 | |
| LEC(S式) | 31.0 | |||
| TAC | 112 | 36 | ||
| ユーキャン | 167 | |||
| 大原 | 45 | 2021年実績、2022年未公開 | ||
| 伊藤塾 | 🥇199 | |||
| クレアール | 125 | |||
| スタディング | 160 | |||
| 資格スクエア | 26 | 開講初年度、該当講座4ヵ月コースのみ | ||
| 藤井行政書士 | 除 | |||
| リーダーズ総合研究所 | 除 | |||
| 東京法経学院 | 除 | |||
| オンスク.JP | ||||
| 大栄 | ||||
| キャリカレ | ||||
| L・A | 除 | 販売停止 |
追記)
✅2023年実績、2024年2月15日アガルート公開 56.11% 303名
合格率を比較
まずは最も気になるであろう%表記(合格率)ですが、明記していたのは3社に限られます。
| アガルート | フォーサイト | LEC | LEC S式 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 56.1 | 45.4 | 公開前 | 公開前 |
| 2022 | 56.1 | 54.1 | 48.8 | 31.0 |
| 2021 | 42.1 | 38.0 | 53.8 | |
| 2020 | 67.2 | 41.3 | 45.7 | |
| 2019 | 72.7 | 42.6 | 未販売 | |
| 2018 | 46.7 | 37.3 | 未販売 | |
| 2017 | 65.5 | 42.8 | 65.7 | 未販売 |
高い・低い以前に前提として合格率表記は信頼できるのでしょうか?
一定の信頼性はあると考えます。
ただ、無条件で信用する必要もありません。
各社の集計方法を見てみましょう。
LECの合格率集計方法
※2022年度パーフェクトコース・パーフェクトコースSP(合格に必要なインプット講義・演習・模試をパッケージ化した商品)を申し込まれた方のうち、コース内に含まれる模試3回全てを受験し、いずれか1回でも模試の得点が180点以上を超えた方の合格率です。
※2023年3月31日時点の情報です。
出典:https://www.lec-jp.com/gyousei/kouza/start/
ポイントは
とはいえ、LECの模試は基本難しく、合格点を出せる方は実力者であると言える。
本試験でもそれなりの結果は出ているはず。
とはいえ、3回中1回と考えたら、実際はもうちょっと低いのではないでしょうか。
アガルートの合格率集計方法
アガルートはアンケート方式。
合格発表日にメールでアンケートフォームが送られてきます。
合・否・棄権の3択
その他講座の選択理由などを記入。
アンケートのお礼はアマギフ(Amazonギフトコード1.000円分)。
自己申告制ではあるものの、証明画像(通知書・合格書)を名前付きで求められるので、虚偽は難しい。
よって、一定の信頼性はおける。

ちょっとギフトもらえるからって、落ちた人は答えたくないピヨ。
こういいたい気持ちもわからないでもありません。信じたくないほど高いですよね。
合格者数・合格率共に公開されているため、アンケート回答数もわかります。
何万人も受講しているとは考えられないので、統計的には一定の信頼性はある数値。
ただ、分子・分母共に少ないため、%表記ではぶれが大きく出るもの事実。
フォーサイトの合格率集計方法
基本的にはアガルートと同様です。
ただ、気になる点があります。
2022年は2021年と違い、なぜかバリューセット2に限定されている。
※弊社集計の受講生アンケートに基づくデータです。
フォーサイト公式サイトより
※2022年度行政書士試験のバリューセット2の受講生実績です。
同様に、2023年は2022年と違い、バリューパック3に限定されている。
※弊社集計の受講生アンケートに基づくデータです。
フォーサイト公式サイトより
※2023年度行政書士試験のバリューセット3の受講生実績です。
この2つめの※が、「○○時間以上勉強した人」の年や未記入な年もありました。
この点から、手放しに信頼できる数値ではありません。
- サンプルテキストの内容の深度
- 公開講義の内容の掘り下げ程度
- 講義の総時間
- 企業方針
これらから見て、合格点ぎりぎり目標の講座(要点集約型と呼んでいます)であることがわかります。
要点型で、50%(2022年54.1%)を超える合格率は異常値。
では「嘘」なのか?と言われたらNO。
虚偽は企業として得られるメリットよりはるかに高いリスク、やる価値も、意味もない。
高確率で真実。
だからこそ「バリューセット2」や「○○時間以上学習した人」など年によって限定内容が異なるのでしょう。
合格者数の表記(2021年200名)が消えた点からも…‥。
勘違いしないでいただきたいのは、これらの点を考慮しても要点型のなかでは抜群に高い実績を出せるスペックであることも事実。
網羅性の高い予備校系より高い数値をコンスタントに出すことは不可能。
しかし、的がハマれば爆発的な効果が出る、はまった年だとみることもできる。
合格率の算出には金も時間も手間もかかる。
合格率を出しているのは、18社調べて3社です。
なぜこんなにも記載されないのでしょうか?
いくつも理由があるとは思いますが、大きい理由として「合格率を出す必要がない」
こういった調査にはどうしても、費用と手間がかかります。
何の見返りもないアンケートに答えてくれる人はごく少数です。
見返りがあったとしても、アンケートの回収率は高くない(一般的なアンケートで回収率30%程度)。
さらに、行政書士試験の合格者は全員で5.000人程度。
各社それなりに合格者を排出しているとしても、せいぜい数百人。
分子が小さい分、わずかな偏りで数値はぶれる。
低いと受講者が激減し、高いと嘘くさいと言われる。
費用も時間も投入して集計してまで、出す側にメリットは多くない数字です。
また、少数で運営しているため、人力的に出せないところもあるでしょう。
数値的に出したくないところもあるかと思います。
なによりも、業界的に実績出さなくても、支障がない。
公表していない企業のほうが多いのだから、金も時間もかけて集計する必要はない。
各社様々な思惑で実績を公開していると考えるのが自然です。
結局、合格率表記は信頼できるのか?
一定の信頼性はありますが、無条件で信じるものでもありません。
信じるべきは、費用と労働力を割いてまで、受験生の知りたい数字を出そうとしてくれる姿勢であると言えるのではないでしょうか?
合格させるためのサービスが講座です。
実績出してなんぼ。
価格や内容をいかに誇ろうが、実績に及ぶものではない。
その中で、合格率は特に知りたいであろう数字。
分母分子がが少なく、大きくぶれる数値であるとこは事実だが、出そうという姿勢が受験生のニーズを酌んでいるともいえる。
より、受験生が求めるものを提供できる可能性が高いと思っても何ら不思議ではない。
合格者数
進学とは違い通信は、合格者数を正確に把握することはまず無理。
合格者は(体験記数も)最も少ない数であると考えるのが自然。
表記された数以上に合格者がいることは確実。
| 年度 | アガルート | フォーサイト | スタディング | ユーキャン | TAC | 大原 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 296 | 未公開 | 160 | 167 | 112 | 未公開 |
| 2021 | 217 | 200 | 90 | 233 | 118 | 45 |
| 2020 | 59 | 167 | 164 | 76 | ||
| 2019 | 215 | 149 | 65 | |||
| 2018 | 272 | 169 | 73 | |||
| 2017 | 323 | 232 | 136 | |||
| 2016 | 282 | 125 | 88 | |||
| 2015 | 370 | 169 | 200 | |||
| 2014 | 265 | 149 | 183 | |||
| 2013 | 393 | 193 | 192 | |||
| 2012 | 398 | 197 | 231 | |||
| 2011 | 223 |
空欄多くてすみません。
「未公開」は前年公開していたのに、人数表記をしなくなった企業。
この辺も各社の思惑が見て取れる。
合格者数は最小値
各社集計方法は主にアンケート。
合格率と異なる点は、確実にこの人数以上の合格者がいる点。
合格者数として公開されている数値は最小値。
となると、問題はアンケートの回収率がどの程度か?という点になるが、正確な数値を出すことは不可能。
ただ、一般的にアンケートの回収率は10~40%の範囲で、概ね30%程度。
後反転攻勢が予想されます。
合格体験記も合格者数同様必ずその数以上の合格者がいる
合格体験記自体は概ねどの企業でも掲載はされている。
しかし、過去と混同していたり、年度不明は除外しました。
また、合格者数が明記されていた講座も重複するため集計してません。
| 伊藤塾 | クレアール | LEC | 資格スクエア | |
| 2022 | 199 | 125 | 53 | 26 |
| 2021 | 128 | 90 | 69 |
集計方法はこちらもアンケート。
単に合否を回答するアンケートより回答率は低いと考えるのが妥当です(記入事項が多く文章量が求められるため)。
2022年であれば、199+125+53+26=403名が合格者数の最小値。
合格者のどれくらい講座を利用しているのか考えてみた。
合格者のうち、どのくらいの人が講座を使っていたのか?
受験時代かなり知りたかった点です。
正確な数字は出ません。
ですので、数字遊びになります。
興味のある方だけご覧ください。
合格者数+合格体験記=最低合格者数
①2022年の合格者数各定数
| アガルート | スタディング | ユーキャン | TAC | |
| 2022年 | 296 | 160 | 167 | 112 |
296+160+167+112=735名
②2022年の合格体験記記載数
| 伊藤塾 | クレアール | LEC | 資格スクエア | |
| 2022年 | 199 | 125 | 53 | 26 |
199+125+53+26=403
③合格者数+合格体験記記載数
735+403=1.138名
2022年講座利用合格者の最低数が1.138名。
思ったより多いでしょうか?少ないでしょうか?
アンケート結果ですので、アンケートの回収率で利用者概数を憶測することができます。
アンケートの一般的な回収率は30%前後
一般的なアンケートの回収率は30%前後です。
例えば、令和2年国勢調査では、ネット回収率が37.9% 郵送が41.9%
回収率はアンケート内容や実施する団体、その他の要素により変わってきます。
CS(Customer Satisfaction・顧客満足)調査は30%よりも回収率が低いのが一般的です。
講座の合否アンケートはCS調査であると言えるので、かなり高く見積もって30%
回収率が低ければ低いほど推定合格者数が増えて、20%で全体の合格者とほぼ同数になってしまします。
40%以上の回答率は性質上、高すぎる。
よって、30%程度でそこまで大きくずれない推測が可能ではないかと考えます。
合格体験記のほうが、合否を返答するだけのアンケートより回収率が低いのですが、分けるとややこしさがさらに増すので、かなり大雑把にまとめて高い回収率(合格者数を低く見積もって)で見ていきます。
余談ですが、どこで、どのように得た数字がお伝えすることはもろもろの事情でできません。なので、あくまで余談としてですが、ある合格者数を出している講座の合格者数がアンケート結果の3倍の数把握しています。なので、回収率30%は的外れな数値ではないと考えています。
講座合格者の割合は?
仮にアンケートの回収率が100%であった場合
- 2022年各講座の合格者数+合格体験記記載数=1.138名
- 2022年行政書士試験合格者 5.802名
- 占有率 19.6%
アンケートの回収率によって推定合格者数出してみます。
| アンケート回収率 | 推定合格者数 | 占有率 |
| 100% | 1.138 | 19.6% |
| 50% | 2.276 | 39.2% |
| 40% | 2.845 | 49.0% |
| 30% | 3.755 | 64.7% |
| 20% | 5690 | 98.0% |
この集計において実績非公開の企業は数に含んでいません。
全く実績がないが数年間も販売を継続するとは考えにくく、現にL・Aは2020年を最後に販売を停止。
つまり、ビジネスとして成立するだけの売り上げがあり、相応の結果が出ていると考えるのが自然です。
これらを考慮して、回収率30%が妥当だとすると、合格者の70%程度が講座出身者ではないかと考えます。
30%は希望になるか?
講座合格が全体の70%だとすると、残りの30%が独学になるわけです。
ただ、この中にロー生・予備試験組・司法書士試験組など猛者たちも含まれていれば、(当年は独学の)複数年受験生も入ってきます。
講座の合格率・合格者数が教えてくれるのは現実的な勝ち筋を選べるかどうか
独学で合格は可能です。
誰にでも可能性はあります。
ですが、それは10人に1人の世界ではありません。
講座や法学ガチ勢など、多くの投資を行った人たちが優先的に勝ち残っています。
全体の合格率が10%程度の試験であることは変わりません。
しかし、残念ながら格差社会。
それでも独学で修羅の国で勝ち抜くすべがないわけではありませんが、厳しい現実があることだけは確かです。
独学合格者の私が、予備校系の講座を強くすすめるのは勝つ確率の高い選択肢を選んでいただきたいからです。