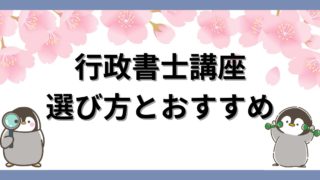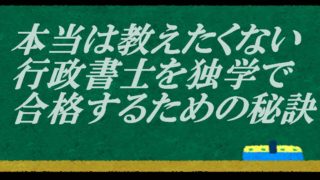「勝負の夏」は大学受験で用いられていましたが、行政書士試験においても「夏を制する者が勝負を制す」といっても過言ではありません。
時期的に過去問の周回は順調でしょうか!?
過去問を順調に進めていればいるほど、「あいつ」の存在が気になってきますよね。
- 40字記述式問題
- 一般知識
- 商法・会社法
- 基礎法学
人によって悩みどころは違います。

私はすべてでした。
- 記述対策もしなければ怖いし、
- 足切り怖いし、点数ちょっと上積できれば楽になるから一般知識対策もしたい。
- 会社法もやらなきゃ・・・・・。
あれもしないと、これもしないと・・・・・。
結局、いろいろ考えた末に、ある程度バッサリ切り捨てました。
切り捨てないと、肝心な憲民行が仕上がる気がしなかったから。
何をして、何をしないかをはっきり決めよう。
もちろん、弱点や不安要素なく進めるのであれば、それに越したことはありません。
順調であればいいのです。
何をとって、何を捨てるのか?
それで合格が可能なのか?
など、より具体的な戦略が必要になってきます。
最も怖いのはどれも中途半端になってしまうことです。
この記事を通して主要な夏の悩みを解決するヒントになればうれしく思います。
- 記述
➡高得点を狙わなければ記述は難しくない。
➡記述で何点必要ですか? - 一般知識
➡文章理解と個人情報保護法を極めよ。
➡政経社で2問取れなかった年はありましたか?
➡文章理解はコツもテクニックもあるが魔法ではない。 - 商法・会社法
➡どこまでやるか・捨てるか決断の時。 - 基礎法学
➡対策がどうしても必要ですか?
今回の内容はあくまで、ある程度勉強が進んでいる人が対象です。
行政書士試験の配点や合格・足切り基準などわかっている前提で話を進めることご承知ください。

当然ですが、あくまで個人の意見です。
どの記事も同様ですが、
結果に関しては一切責任は負いませんし、負えません。
「こういう考え方もあるんだ」くらいにとらえてください。
そのうえで、どうするのかは「あなたが決めることです。」
【決断の時】何を捨てるのか?何を拾うのか?
大前提として、憲法・民法・行政法の択一対策に手を抜くという選択肢はない。
この3科目はメイン科目です。
そんなことはすでに知っているはずです。
でも、実際に勉強を進めていくと、

記述も一般知識も会社法もやらないと不安でしょうがないのです。
こう感じている方、多いのではないですか?
だって、私も同じだったから。
計画を修正できるのは夏がラストチャンスです。
- 記述は何点必要ですか?
➡20?30?40?
➡必要な点数で対策は変わります。 - 一般知識は何点見込めますか?
➡文章と個人情報系はマスト - 商法・会社法をやる?捨てる?
➡捨てる代わりに何をする? - 基礎法学は対策がどうしても必要ですか?
40字記述式問題であなたは何点必要ですか?
得意な人などいるのでしょうか?
配点が非常に大きいため捨てることはできません。

記述で満点とるのは至難の業です。
ですが、満点を取る必要はありません。
記述に関しては、模範回答以外は年度により調整の度合いが全然違います。
なので、「こうすれば半分は取れますよ」みたいなことは言えないのです。
満点回答できる受験生はまずいません。
予備校の解答速報でさえ、各社微妙に違っていたりします。
確実に言えることは
- 過度な期待はしないこと
- 記述でどの程度点数を見込むのかで対策は変わってくる。
高得点を狙わなければ、記述は難しくない。
記述が難しく感じるのは
- 何が問われているかわからない。
- どう書いてよいかわからない。
の2点が多いと思います。
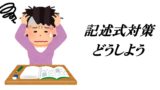
では、当時最新の平成30年の記述から一問例を上げました。
同じく現行最新の過去問である令和2年から例をあげてみましょう。
令和2年の44問(問題自体を掲載することはできません。お手持ちの過去問集をご覧ください)
では、問題文のXは
- 誰を被告に
- どのような行為を対象に
- どのような訴訟を提起すべきか
を聞いてきています。
この段階で穴埋め問題に変わります。
○○を被告として、△△を対象に、✖✖訴訟を提起する。
あとは、○○、△△、✖✖はどれも過去問レベルの知識です。

この問題に関しては、「無効【等】確認の訴え」でもよいのか「無効確認の訴え」でなければ点が入らないとかいう噂もあります。
この手の噂が出てくるほど、厳しい採点であったと言えます。
このように考えてみれば、記述はそれほど難しくないと感じますよね?
実際その通りです。
でも、あくまで記述で高得点を狙わない、狙う必要のない戦略の話です。
記述でそれなりの点数が必要なのであれば専用の対策は避けられない。
60点満点の記述で20~30点をとるためには特別な対策は必要ないと考えています。
(点数は平均的な採点がされた場合を想定しています。R2では10~20点、R1は30~40点、H30は20~30点くらいのイメージ、完全に私見ですのであしからず)
(平均的な採点がなされたとしても)30点以上を狙うのであればそれなりの対策が必要になってきます。
先の例と同じ年、令和2年第46問(問題自体を掲載することはできません。お手持ちの過去問集をご覧ください)を見てください。
この問題
- 背信的悪意者からの転得者は、転得者が背信的悪意者でなければ対抗関係になる。
択一対策としてだれしもやっているはずです。 - さらに、177条の第3者は平成21年に記述で出題されていたりします。
有名な「当事者もしくは包括承継人以外で、登記の欠缺を主張するに正当な利益を有するもの」(・・・・記憶だけで書いてますので多少違うかもしれませんが大目に見てください。)です。
背信的悪意者は第3者にはあたらない。ってやつですね。
ここまでは、誰でもやっているはずです。
ですが、これでは書けません。

この問題、くそ難しくないですか?
本番でかける自信は・・・・ありません。
行政書士受験生なら誰しも勉強する有名判例でありながら、ここまで把握していた受験生がどのくらいいたのでしょうか?
択一対策として、単に結論知っているだけでは歯が立ちません。
独学殺しの問題です。
一方で、法学部出身者などから見ればさほど難しくはない問題のようです。
基礎の部分ではあるようですが、私のように行政書士試験受験のために初めて法律を勉強した人にはかなり厳しい問題であったと感じます。
受験当時のテキスト引っ張り出して確認してみましたが、記載はありませんでした。
もちろん、アガルート入門総合カリキュラムでは、テキスト・講義ともにしっかりと記載がありました。(レビュー用に2021年度対策受講させていただいています。ちなみに2021年度対策講座は2020年度8月、令和2年度本試験より前に販売開始されています。)
この問題に限らず、専門的な教育を受けているか否かで差が出る問題が記述でも出題されるようになってきたという印象が強いです。

この一問が、難しかったというだけで、決めつけるのは無理があるピヨ。
と思うのもわかりますが、前年の令和元年度では、過去一度も出ていない論点からの記述の出題がありました。(こちらも、当時使用していた著名な市販テキストではテーマの記載すらありませんでした。)
2年続けて、未出題と過去問既出ではあるものの、より踏み込んだ内容の出題でした。
そのうえ、採点を厳しくしなければならなかった点から考えても、次年度以降さらなる難化が容易に予測されます。
記述で高得点を狙うのであれば、この手の問題でも対応できる必要が出てきます。
どのように記述対策をするのか?
選択肢はいくつかあると思います。
- 行政書士用記述式専用単科講座の受講
- 行政書士記述対策市販問題集の使用
- 他資格問題集の使用
- 対策しない
高得点を狙う選択肢を選ぶのであれば、①記述専用単科講座の受講 一択です。
もちろん、受講すれば点が取れるといった簡単な話ではありません。
ですが、メリットは大きく、択一の強化にもつながります。
過去問や予想問題などである程度解法に慣れてきているのであれば
④対策しない
も選択肢に入ります。
択一過去問ぐるぐるしかしていないのであれば、②記述専用市販問題集 で解法に慣れておく必要はあります。
過去問知識がしっかり固まっているのであれば、そこまで時間はかからないと思います。
記述専用単科講座の受講
記述である程度の得点を目指すのであれば、受講を考えるのもありです。
単科講座ですので価格はそこまで高額ではありません。
メリットは、
- 問題の読み取り方がわかる。
- 具体的な内容からどの条文・判例を当てはめていくのか思考のプロセスが学べる。
- 条文・判例をどのようにまとめていくのか、解法がわかる。
- 周辺知識の確認もできる。
- 結果として択一対策にもなる。
- 総まくり記述80問攻略講座
15時間 38.280円 担当講師、豊村慶太、アガルート
- 記述式 解法スキルマスター講義
 3時間 6.000円 担当講師、平林勉、伊藤塾
3時間 6.000円 担当講師、平林勉、伊藤塾 - 記述60問解きまくり講座 7時間30分 22.000円 担当講師、横溝慎一郎、LEC
- アガルート3月から
- 伊藤塾9月から
- LEC7月半ばから
対策しないのが対策
先にも触れましたが、高得点を狙わないのであれば特別な対策は不要です。
その分を商法・会社法や択一対策に回しましょう。
決して、勉強時間を減らすということではありません。
何を捨てて、何を拾えば合格が現実的になるのかを考えましょう、という話です。
記述専用市販問題集
やらないよりは、やったほうがいい。
しかし、過去問をしっかり学んでいれば、それほどメリットがあるわけではないと考えます。
とはいえ、肢別と1000問ノックはじめ、択一過去問しか勉強していない方は、解法を学ぶ上で一冊はやっておいたほうが良いと考えます。
通販より、書店で直接手に取って、見やすいものを選ぶとよいでしょう。
模試や予想問題集の数をこなしているのであれば、必要ないかもしれません。
ただ、いずれにして高得点を狙うというよりは、解法になれるという使い方になると思います。
最悪手、市販他資格問題集
記述対策として市販の他資格問題集は最悪手です。
傾向も、出題深度も違う他資格問題で記述対策は極めて難しく、非効率です。
他資格問題集やるくらいなら、択一の精度高めてください。
そのほうがよほど記述の点が伸びる可能性が高まります。
会社法捨てないでください。
そのほうが、点数伸びる可能性が高まります。
というレベルの話です。
もう勉強やりつくしてほかにやることがないという人ならワンちゃんアリですが、、、、、そんな人いますか?

あくまで独学者が市販の他資格問題集を使うことが悪手であると言っています。
プロの処方を受けたものは全く別物です。
他資格問題は処方薬に似ている。
ドクターに処方された薬は高い効果を発揮する可能性が高い。
逆に素人判断で薬を乱用してもいい結果にはならない。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
記述対策まとめ
あなたが合格を勝ち取るために、記述で何点必要ですか?
これが最も大切です。
- 20~30点程度であれば、そのレベルまで択一が取れる実力があれば特別な対策は必要ありません。(最低限解法に慣れておく程度の対策は必要な人もいる)
- 30点以上の点数が必要なのであれば、記述用の専用単科講座を受講しておきましょう。
記述で高得点が必要なのは、何かしらの分野が苦手であるか、捨て分野を作るからだと思います。
会社法と基礎法学が0点でよいので、記述の対策
これは(おすすめしませんが)ありです。
商法・会社法・基礎法学の計7問、番号決めてマークしても1問は確率でGETできるはずです。
運が良ければ2問の可能性も低くはありません。
それで合格できる絵がかけれるのであればそれでよいわけです。
くどいようですが、何を捨てて何を拾いますか?
政経社やりたい気持ちはすごいわかる。でも、一般知識はセオリーで進めよう。
配点が56点と行政法、民法に次いで3番目に大きいのが一般知識です。
さらに、24点、6問未満は問答無用で不合格が決定する足切り制度も恐怖です。
近年の合格者は一般知識8問以上確保しているという情報も出回っています。
そのため、しっかり対策をしたくなるのが一般知識。
ですが、あえて言います。
セオリーでGO!
一般知識対策は個人情報保護関連法と文章理解を極めよう
典型的なセオリーですが、個人情報関連法と情報通信・文章理解で点を稼ぎましょう。
これで5問は狙えます。
人によっては6問GETしてしまいます。
- 個人情報保護法系は得点源
- IT用語が苦手、、、、これは得手不得手が分かれるところです。
- 文章理解が苦手はパターンがわかれる。
➡時間かければ取れるのか?
➡時間をかけても取れないのか?
で対策はかわる。
一般知識に関しては

でも詳しく解説しております。
個人情報保護法系は得点源になる。
個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、情報公開法まれに公文書管理法などから出題がありますが、そこまで細かく難しい内容の出題はありません。
理解より暗記寄りの科目です。
行政法だと割り切って過去問反復と定義の暗記で乗り切ることは可能であると考えます。
不確定要素の多い一般知識で安定した得点源になる科目です。
情報通信関連は得手不得手が分かれるところ、ざっくりでOk
特別な対策の立てにくいうえに、得意な人には難しくない。
苦手な人はとことん苦手な、なんとも人を選ぶ分野です。
どうしても苦手ならスルーするのも手です。
過去問も現在とは状況が変わっているものもあります。
そのため、問われ方を知っている必要がありますが、過去問ぐるぐるは基本役に立たない分野。
対策としては、
- 行政書士の監督官庁である総務省の「国民のための情報セキュリティサイト」を気分転換程度でチラ見。
- 知らない情報系の言葉を聞いたら忘れないうちにググる。
くらいじゃないかと思います。
コツは細かく覚えない、ざっくり意味が分かればOK。

令和2年の過去問でSSLやHTTPなどが出題されていました。
「ハイパーテキスト・・・・・・・」などと正確に暗記する必要ありません。
ざっくり、SSLは暗号通信のことだな、くらいでOkです。
ちなみに、HTTPSってHTTPがSSLやTLS(SSLの進化系くらいでOK)で暗号化されている状態です。
文章理解は時間をかけてでも確実に3問とる
一般知識攻略のカギとなる文章理解、確実に3問全問正解したいところです。

実際の本試験では、政経社の出来を見てかける時間を判断するという手もあります。
ですが、準備段階では時間を使ってでも3問きっちりとるつもりでいたほうが良いでしょう。
なぜ、そこまで文章理解が重要なのか?
- 国語だから。
- 取れるところで確実にとらないと合格は厳しいから。
ややこしい民法や抽象的な憲法の理解をしてきているのですから国語力は相当程度持ち合わせているはずなのです。
まずは過去問で以下の点を確認してください。
- 時間をかければ取れる?
- 時間をかけても間違うのか?
勘違いしている人もいますが、
- 確かに文章理解にテクニックはあります。
ですが、知っていればすらすらとけるような魔法ではありません。
むしろ、得意な人は無意識レベルで行っています。 - 文章理解においては過去問の反復に意味はありません。
間違えた問題は何が読み取れなかったのか?どこに注意すべきであったのか?を理解するために再度解くのは効果的です。
が、同じ問題を何度も繰り返して実力が付くものではない。なんでもかんでもやみくもに繰り返せばよいというものではありません。
時間をかければ正解できる人
じっくり文章を読んで解けば、かなりの人が正解できると思います。
重要なのはどのくらい時間がかかったのか?

私は文章理解一問で10分、最大15分と決めていました。
文章理解と記述で試験時間の半分(90分)を消費してもかまわないと考えていたのです。
もちろん、同じようにしてくださいというつもりはありませんが、時間をかければ解けるのであれば時間配分はとても大切になってきます。
ただし、一問20分くらいかかるようであれば、対策は必要になってきます。
時間をかけたら解けるけど、時間がかかりすぎる人の文章理解対策
時間がかかりすぎる人の対策は、慣れることで解決する場合が多いです。
正解は出せるわけですから、文章自体は読めています。
文章に慣れていない。
読むためのコツがつかめていない。
これらの可能性が高いと考えます。
よって、慣れてしまえば時短は十分に可能であると考えます。
おすすめはセンター試験用現代文の参考書・問題集です。
数が多すぎてどれがおすすめとはいえないのですが。。。。。。
時間をかけても間違ってしまう場合
直近5年の15問で正解が10問未満
または、同一年度で2問以上不正解の場合
早急な対策が必要になります。
といいますのも、文章または選択肢が読めていない可能性が高いと考えます。
文章理解の実力は一朝一夕で身につくものではありません。
そのため、直ちに取り掛かる必要があります。
時間をかけても間違ってしまう方への文章理解対策
時間をかけても間違ってしまう場合、
- 感覚で読んでいる。
- 著者の主張が把握しきれていない。
- 接続詞、指示語を意識して読んでいない。
- 内容を決めつけてしまって、勝手に解釈している。
などが考えられます。

同時に多肢選択式も確認してみてください。
多肢選択式も国語的な文脈から答えを推察できる場合が結構あります。
10代の若い人ならともかく、社会人が短期間で文章の読み方の癖を修正するのは簡単ではありません。
行政書士試験対策のみならず、合格後に開業や他資格に挑戦するつもりであれば、今後より難解な文章が出てくることが予想されます。
そもそも、判旨が長文かつ難解ですよね?
できれば、大学受験予備校で現代文の授業を受けたいところですが、難しいと思います。
次善の策として、行政書士試験対策用の文章理解単科講座の受講をおすすめます。
文章理解 解法スキルマスター講義 ![]() 3時間 6.000円 担当講師 森広志 伊藤塾
3時間 6.000円 担当講師 森広志 伊藤塾
文章理解対策講座 4.5時間 14.800円 担当講師 田島圭祐 アガルート

パッと見、値段が全然違うように感じるピヨ。
ただ、田島先生は大学受験予備校にて18年以上国語指導をされている人気講師ピヨ。
田島先生のサンプル講座ありますので共有しておきます。
ザ・現代文の授業という感じですね。
アガルートはかなりのサンプル講座を提供してくれるので非常にイメージがつかみやすいですね。
とにかく我流でやらない。
行政書士の文章理解は現代文として決して難しいものではありません。
読解力は試験だけでなく様々な分野で広範囲に役に立つ能力であることは言うまでもありません。
読む力が苦手であると自覚し、対策を講じ、苦手を解決する。
人によっては資格を得ること以上に価値ある行為になるかもしれません。
政治・経済・社会は過去問を使え!ただし、回転するんじゃない!!
政治・経済・社会ですが、夏以降非常に対策したくなります。
気持ちは非常によくわかります。
やる・やらないはいったん置いておいて、まずは過去問をやりましょう。
見るべきポイントは2つです。
- 過去10年で政経社で2問以上取れなかった年はあったのか?
- 取れなかった問題は、知識がないと取れない問題であったのか?
過去10年の過去問で政経社が2問以上取れなかった年はあったのか?
文章理解で3問
情報通信・個人情報保護で2~3問確保できるのであれば、
足切り回避までに必要な残りは、0~1問です。
とはいえ、近年の合格者が一般知識8問程度取れている人が多いという話もあります。
できれば8問はほしいと思いますよね?
そこで確認していただきたいのが、過去問・予想問題・模擬試験で政経社全滅した年があったのか?
2問以上取れなかった年度があったかどうかです。
安定して2~3問程度取れているのであれば、7~8問取れていることになります。
政治・経済・社会は勉強しても意味のない科目ではありませんが、費用対効果の極めて悪い科目であることは事実です。
取れなかった問題は、知識がないと取れなかった問題でしたか?
年度別に何問取れたのか?も重要ですが、もう一つ過去問をやるうえで振り返ってほしいポイントがあります。
落とした問題は、知っていないと正解が出せない問題でしたか?
例を出したほうがわかりやすいので、現時点で最新の過去問から
令和2年問題53を見てみてください。(問題そのものを掲載することができません。)
肝になるのは選択肢の「ウ」ですね。
「大都市の都心部に地方の若者を呼び込む目的」
これなに?ってなりませんか?
過疎化している地方に若い人が来てほしいってのはなんとなくわかるじゃないですか。
逆に、都会、例えば渋谷などはほっておいても若い人たちは集まって、交流してくれそうじゃないですか?
そんなものが地域活性になるかといわれたら・・・・・。
ってのは、感覚でわかりますよね?
そうなると、「イ」と「オ」のどちらかが判断できれば正解にたどり着けるわけです。
「イ」の肢はなんとなく、その通りかも、くらいでよいわけです。
肢の「オ」で「中心都市の自治体が主体となって、民間の力を借りずに地域活性化を図る」の部分
これって、おかしいですよね?
行政単独で地域活性化を図る意味がわかりません。
自治体も、地域の学生や企業と協力したほうが、盛り上がる可能性高いじゃないですか。
このように、個別具体的な知識ではなく、世の中の流れである程度判断できませんでしたか?
確かに、ある程度の知識がないと解けない問題もあります。
ですが、世の中の流れや一般常識で「それはないだろう」
「そりゃそうだよね」で正解にたどり着ける問題もしっかりと用意されています。
また、あなたの人生経験によっても大きく変わります。

例えば、私は経済学部出身ですので、令和2年49問などは見ただけでパシッと答え出るのです。
かつての島の問題やペットショップの問題のように、奇問も出てくる可能性は今後も否定できませんが、全部が奇問という年は今のところありません。
反対にギャグのような問題もあります。
平成29年問題52のイとか面白いですね。
「自己破産が年100万人」といった記載があります。
さすがに、多すぎですよね。
年100万人も自己破産していたら、10年で1000万人、10人に1人は自己破産してるとかありますか???
政経社の過去問で学んでいただきたいのは、「何がわかれば正解にたどり着けるのか?」を知るという点です。
例えば、少子化が進んでいるという誰でも知っている知識だけで推測できるのか?
それとも、何%という具体的な数字を知っていないと解けないのか?
この準備なしに、やみくもに過去問を回転させてみたり、必要のない深度まで入り込んでも、時間だけが過ぎ去っていくだけです。

5~10年前と今では状況が全然変わっている部分も結構あるピヨよ。
忘れてはいけないことは、一般知識は全問正解する必要はまったくもってない。
足切り回避が目的で、8問程度取れれば勝ちといっていい科目である。
政治・経済・社会の対策は?
ここで初めて、政治・経済・社会の対策が必要か否か判断してください。
- 全く何もしなくても、足切り回避はクリアーできる人はクリアーできます。
- 何もしないと精神的に不安でほかの科目に集中できないというのもわかります。
- 憲民行の進捗度合いによっても変わります。
よって、どの程度のレベルで対策するのかは人により大きく異なる分野です。
行政書士試験のキーはあくまで憲法・民法・行政法です。
一般知識対策の軸は、文章理解と個人情報関連です。
政経社は深入りしすぎない程度に対策をするならば行ってください。

個人的には気分転換にちょこっとやるのがいいと思います。
5分とか、10分くらい一日の最後でもよいですし、勉強始める前の集中力を高めるための起爆剤代わりにしてもよいと思います。
おすすめは教材は
豊村慶太の政経社ポイント講義・・・・・誰でも15回の講義が視聴できます。
できれば、歯車の設定から速度を1.75倍で見ることをおすすめします。
注)動画を見る際は公式サイトからにしておいたほうが良いです。YouTubeで見てしまうと、どんどん興味深い動画が紹介されて気が付いたら勉強する時間が無くなっていたりします。YouTubeの誘惑やばいですよ。
もう一点は、私も使っていた公務員試験用のテキスト
![]()
事細かに覚える必要はありませんし、全部読む必要もありません。
必要そうなところだけ、拾い読みで十分です。

どのが必要そうで、どの程度の内容まで読むのかを知るために先に過去問を分析するのです。
商法・会社法はどこまでやるのか?捨ててしまうのか?
商法・会社法に関しては非常に悩むところですね。
やるか、捨てるか決めるべき時期になりました。
やらないと不安だけど、時間的な制約がきついという人は、頻出分野に絞った対策もまだかろうじて通用する科目です。
この話だけでも、かなり長くなりますので、
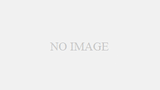
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
まとめると
- 商法・会社法を捨ててしまうのは基本おすすめしない。
- 勉強しても得点が見込めない分野がほかにもあるため、捨ててしまうリスクは高い。
- 反面、主要科目(憲民行)が中途半端になるくらいないら、思い切って捨ててしまって、主要科目に注力したほうがよい。
- 基礎法学・政経社・憲行の他資格問題は商法・会社法より学習効率が低い。
- 頻出分野に絞った学習が会社法ではまだ通用する(主要科目では厳しくなっている)。
- 頻出分野に絞った学習であればコスパは悪くない。
基礎法学の対策はどうすればよいのか?・・・・どうしようもない
取れる問題と、取れない問題の差が極端なのが基礎法学。
出題は、たったの2問8点です。
そのうえ、過去問での対策がかなりむりげーな科目です。
過去問ではなんとなく、「裁判関連」と「法律用語」の出題頻度が高いかな?
と感じる程度。
範囲も漠然としていて、どこからでも出題可能であるため、対策は難しい。
時間を投入しても、政経社以上に費用対効果は悪いと言えます。
できることといえば、
- 今使っているテキストの内容をある程度把握
- 豊村慶太の速攻チャージ!基礎法学
2時間の講義が無料で公開されています。
くらいではないでしょうか。
これらで得た知識に、憲法の考え方など今まで学んだことの断片から推測して、なんとか一問取れたらラッキーくらいで考えておく必要があります。

勘違いをしてほしくないのですが、基礎法学の対策が全くできないわけではありません。
ただ、とても効率が悪い。
最も費用対効果の低い科目だといっても過言ではないでしょう。
残りの時間が多くない以上、基礎法学に必要以上の時間を投入している余裕はないはずです。
必要最低限の対策にとどめておいて、ほかの科目に時間と労力を回したほうが現実的です。