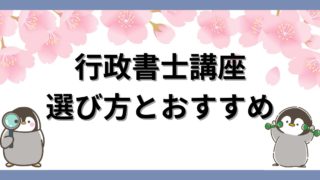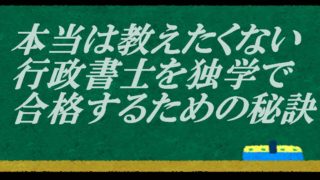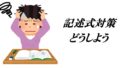さて、行政書士試験で最大の難所と言えば?
法令でいくら点数を稼いでも一般知識取りこぼしたら、足切りで即不合格が確定してしまう恐怖の一般知識です。
正確には行政書士の業務に関連する一般知識等といいます。
法令科目の力が順調についてきている人ほど一般知識への不安は強くなってくるものです。

身に覚えがあり過ぎます。
一般知識、配点(年度により一部例外あり)
全14問、56点
出題範囲
- 政治・経済・社会・・・・7問
- 情報通信・個人情報保護・・・4問(一部例外あり)
- 文章理解・・・・3問
24点(6問)以上取れなければ即不合格確定。
あえて出題構成と配点表を出した理由は
- 一般知識という名前に引きずられない、出題範囲はある程度決まっている。
- 配点が高い科目である。
一般知識という名前に引きずられるな
割と勘違いしやすいのですが、一般知識を一般常識と読み替えちゃうとアウトです。

一般常識なんて漠然としすぎてて、範囲広すぎて対策のしようがないピヨー。
とか思いやすいのですが、それは違います。
ある程度出題分野が決められています。
ただある程度です。
実は憲法より重要度高いのです。
行政書士試験の重要科目3つを上げてください。
行政法・民法・憲法
では、ありません。
行政法・民法の順で重要なのは間違いないです。
ただし、3つ目は一般知識等になります。
憲法は多肢選択入れても配点は28点、比べて一般知識は56点あるのです。
倍ですよ、倍。
一般知識は6問取れたらOK
では、合格するためには行政法・民法並みに勉強しないといけないのか?
という疑問が出てきます。
答えは、NOです。
6問取れればOKです。
理由はコスパが非常に悪いためです。
配点表見てもらえばわかるように、政経社が半分を占めています。
この政経社が曲者で時事を絡ませてきたり、難問奇問が出てきたりします。
一般知識の難易度はセンター試験レベルだとか、有名私立の入試レベルだとか言われてます。
これを安定して得点が見込めるレベルにまで持って来ようと思ったらかなりの時間と労力投入しないと正直難しいと考えます。
逆に常識で判断できる、選択肢を減らせる問題もあるため、よほどのことがなければ政経社全滅ということはありません。
対策に多くの時間を割かなくても1~2問はキープできます。
文章理解、個人情報保護、情報通信で勝負
では、肝心かなめの6問はどうやってとるのか?
狙いは、文章理解、個人情報保護・情報通信、合わせて5~6問が理想的。
プラスで政治・経済・社会で1~2問程度抑えていくことになります。
文章理解
文章理解については3問中3問取りたいです。
情報通信
用語や何を指すのかの問題が多い印象です。
ニュースで見かけた知らない用語は調べる癖をつけておかなければ対応は難しいかと思います。
定番ですが、総務省の「国民のための情報セキュリティーサイト」の用語辞典を一読しておくといいかと思います。
IoTやクラウドファンディングなど出題がありました。情報通信に関する用語は聞いたときに知らなければ即調べる癖をつけておく程度の対策で十分です。というか、他にできません。
個人情報保護関連法
個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・行政機関情報公開法・公文書管理法などがあげられます。最重要は個人情報保護法です。
これは、一つの科目としてとらえてください。
対策は他の法令科目同様、テキスト・過去問が重要になりますが、出題のほとんどが条文です。判例は・・・・・記憶にありません。(見落としがなければ)
定義とそれが具体的に何を指すのか丁寧に抑えていってください。そこまで時間がかかる科目ではありません。
この個人情報保護法と行政機関個人情報保護関連三法(行政機関個人情報保護法・行政機関情報公開法・公文書管理法)は行政法勉強したその足でそのまま入ると入りやすいです。
なぜかといえば、行政法だからですね。
行政法の考え方そのまま使います。
それでも、政治・経済・社会が不安な人は
本試験で一問・二問取れるとしても、政経社がどうしても不安だという気持ちは非常によくわかります。
ですが、深入りすると法令がおろそかになります。
一般知識で偶発的に点が伸びることは十分にあり得ますが、法令科目で偶発的に点が伸びることはまずありません。力を注ぐなら法令科目です。
一般知識は最低限を抑えれば十分です。それ以上に時間を投入していると他に手が回りません。
もっとも、政経社がそもそも得意な方には一般知識は非常に大きな得点源となります
法令は余裕だという方(他資格経験者以外でいるのか?)は恐怖の足切り確実に突破するために最も注力する分野ですね。
一般知識の過去問活用法
政経社
法令科目と異なりざっくり触れればOKです。
どのような問われ方をしているのかを理解することが重要です。
いい例が出てきません情報通信の単語ですが言いたいことはわかってもらえると思います。
【ただし、括弧内ではなく、本文中に表記されている場合はひっかけはある。】
例、H29・問56のイ R2・問55のア・ウ・オ
個人情報保護関連
こちらは、法令科目同様しっかりと過去問活用します。
どこが問われやすいのか、特に定義であったり。適応範囲など頻出であることがわかると思います。
さらに、類似法との比較もよく出されてますね。
比較は「cf.」でテキストに書き込んで相互に比較できるとようにしておくと後々便利です。
文章理解
こちらは何度も解いて正解だ・不正解だということに意味はありません。
問題の形式を知ることはもちろんですが、解説もしっかり読んで「なんとなく正解」ではなく、指示語が何を指しているのか、正解を出すためにはどこに注目するのかなど意識しながら読むことが大切になってきます。
ある程度やってみると、本文より選択肢を先に読んだ方が良いなど、自然とコツが身についてくると思います。
まとめ
- 一般知識は行政法、民法に次いで3番目に重要な科目(憲法の倍の配点)
- 一般知識は6問取れればOK。コスパが非常に悪い。
- 文章理解は確実に3問、時間をかけてでも取る。
- 情報通信・個人情報保護関連法で2問は取りたい。こつはこまめに調べる癖を付ける。個人情報保護法や関連法はテキスト・過去問を中心に条文をしっかりおさえておく。
- 政経社は深入りしない。
- 補足、個人情報関連の過去問は他の法令科目同様しっかりやします。が、政経社の過去問は「どういう問われ方するのかな?」というのが把握できれば十分です。