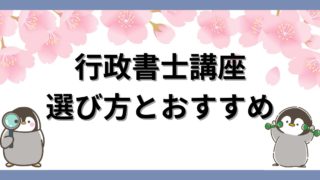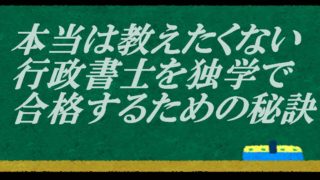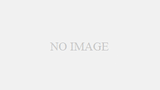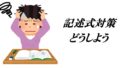行政書士は法律系の資格です。
合格するために何を勉強するかと言うと、当然、法律を勉強するのです。
ではどうやって、勉強をすればよいのか?

条文を全部暗記したりするんですか?

全条文の暗記は、よく誤解されてるんだけど、しない。というか、できない。
法律の勉強だから、資格試験の勉強だからと言って、特別な勉強法があるわけではありません。
高校入試や大学入試との時と基本的に同じです。
ポイントは
- わかるレベルから始める。
- 難しく考えすぎない、イメージしやすいものに置き換えよう。
- 数学に近い、理解して暗記しよう。
- 問題をたくさん解こう
- 繰り返せば、覚えるし、身につく
わかるレベルから始める。
行政書士用のテキストは最初に買ってはいけない、という内容の記事を書きました。
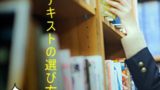
繰り返しになりますが、すごく大事なことなので何度も言います。
行政書士試験用のテキストは行政書士の試験問題が解けるレベルで書かれています。
法律を勉強したことがない初心者がいきなり理解できるレベルで書かれていません。
わかるところから始めましょう。そのためにおすすめの本を紹介しています。
難しく考えすぎない、イメージしやすく置き換えよう。
法律と聞けば難しいイメージが強いわけですが、
法律ってこの国のルールブックですので、
例えば、コンビニで物を買うのは売買契約ですし、住んでいる家が家賃を払っているのなら賃貸借契約がなされているのです。
結婚するときに出す婚姻届けは行政手続きですし、子どもが産まれた時の出生届も同じです。
小難しい言葉がたくさん出てきます。難しい表現もたくさん出てきます。あまり難しく考えずに、具体的に置き換えたり、少々意味が変わってもわかりやすい表現に置き換えたりすると、サクッと理解できたりします。
法律の勉強は数学に近い、理解して覚えるのがコツ
意外に思うかもしれませんが、法律の勉強って理系の人の方が有利だったりします。
この国のルールブックなので、この場合には(要件)、このようになる(効果)。
つまり公式がたくさんできてくるわけです。
そして、その公式には亜種や発展形がたくさん出てきます。
例外は亜種ですし、判例は発展形です。
実際に問題が出てきたら、どの分野のどの公式を使って解いていくのかを判断することになります。
ですので、公式を羅列して暗記するだけではつかえません。
理解が必須です。
ですが、覚えてないものは出てきません。
よって、解き方を理解して覚えるという、数学の勉強に似たやり方になってくるわけです。
具体的な勉強法
ここまで、
- わかるところからやりましょう
- 難しく考えすぎずに、イメージしやすく置き換えた方が理解しやすい。
- 公式がたくさん出てきます。理解して覚えましょう。
ここからは、少し具体的な勉強法になります。
といっても、特別なことをするわけではありません。
基本的には、インプットとアウトプットを繰り返していくだけです。
インプットって何だ?
インプットって知識を入れることです。
具体的にはテキストを読むであったり、講義を聴くであったりするわけですね。
そこで、分かったとわかったつもりになる。
最初は、それでいいんです。
ですが、例えば新聞とかニュースってご覧になります?
今日の新聞とかニュースに何が書いてあったかとかそれに対してどんな解説されていたかとかどの程度覚えてますか?
おそらくほとんど覚えてないと思うんですよ。
これを知識が定着しないというのです。
では、知識を定着していくために何をしていけばいいのかこれがアウトプットと呼ばれるものですね。
アウトプットって何?
端的に言えばインプットの反対です。
問題を解きましょうということになります。
学習の肝になるのが、アウトプットです。
使わない知識は覚えませんし、みにつきません。
学習初期のインプットとアウトプットのバランス
覚えた知識を使って問題を解いていきましょう。
で、ここも、ポイントなんですけどわりとスラスラ簡単に解けると、記憶には残りにくいわけです。
「ここ何やったかな?さっきやったんだよ、ここに書いてあったんだよ。」
こんな感じで、「あのあれ、あれあれあれ、なんかここまで来てるのに出てこない。」
この感覚がすごく記憶に残りやすい。
インプットらすぐに、そのテーマの問題をやってほしい。
そうすることで「これさっき言ってたよね、これさっき書いてあったよね。」
と、気になってテキストに戻る。自分で調べるわけですね。
これがコツと言いますか、記憶に残りやすいアウトプットの方法になります。
完璧主義を捨てよう
テキスト見てもらえば、初めて勉強するに人にとってはかなり細かいところまで書いてある時間を持てると思います。
最終的にはほとんど身につけるわけですが、
最初から全部理解して次に進もうといういうタイプだと辛いです。
なぜ最初から完全に覚えようとすると厳しいのかと言うと、どうしても時間がかかってしまうんですよ、それで周回ができなくなる。これが、致命的なのです。
周回が必要なのは、人の脳は繰り返しに弱いからです。
例えばですよ、ドラマの主題歌とかあるじゃないですか、そこで初めて聞いた時は「いい歌だな」とか、「イメージに合うな」とか思うわけですね。ドラマって大体10回とか11回とかその辺じゃないですか?最終回近くなってくるとその何度も何度も毎回、毎回こう重要なシーンで流れてくる主題歌って自然と覚えてませんか?
あと、子供が好きなアニメ見てるわけですよ。そのオープニングとかエンディングとかで主題歌流れるわけじゃないですか、これも頻繁に聞いてるもんだから意識は特にしてないですけど親の方が覚えてるなんてねいうこともあるわけですね。
「覚えよう」としてませんよね?でも覚えてるわけでしょ。
これなぜかと言うと単に繰り返し、繰り返しですよね。
この一回で完璧に歌えるようになるぞて思ってないわけです。でも結果的には覚えちゃってるんでしょ。
時間かけて1から順番に細かいところまで進めていくよりも、回数こなして行った方が結果的に細かいところまで覚えられるますよ。という話なんですね。
例えば民法を開いてね、被保佐人が保佐人の同意を得なければならない事柄13条1項1から9まで全部覚えます。きついですからね。
進みが悪い→周回できない→ 記憶に残り難い
悪循環ですので、ある程度わかればOK というつもりで周回した方が記憶に残りやすい。
解説は最後の最後
インプットしました、そのテーマすぐに問題解きに行きくわけです。
結構わかりませんよね。
ですが、すぐに解説みるのやめてくださいね。
今インプットしたところに答えがあるので、自分でテキストから引っ張ってくる。
その自分が引っ張ってきた答えが一致してるのかどうかをチェックするのか解説です。
もし仮に、全くテキストに書いてなかったと言うことであるならばメモに書いてテキストに挟み込みしてテキストを強化していくという形で進めていく。
残しておくと次回問題を解いた時に、
「ここにあったよね、確かこれ前もいっぱい調べたけど分からなかった奴だ」
という時の記憶が割と蘇ってくるものです。
記憶を呼び起こしたりとか定着したりしやすいために問題を解くときは解説は最後の最後まで見ない。
むしろ自分の解説が正しいのかどうかっていうのを判断するために解説を使うというイメージでやってもらえればアウトプット効果が高まります。
たくさん問題を解こう
とにかく、たくさんの問題を解いた方が理解がはやいし、覚えます。
学習初期はテキストの内容、講義の内容を覚えるために問題を解いていくわけですが、学習が進むにつれバランスが変わってきます。
学習初期はインプットしてのアウトプットです。
直前期になると、アウトプットでわからないことが出てくればインプットに戻る。
直前期では問題を解くために、テキストを使います。
反復が大切、繰り返せば覚えるし、身につく
問題をたくさん解くのはとても大切ですが、一回解いて終わりでは意味がありません。
何回も繰り返します。

何回くらい繰り返せばよいのですか?

その問題を解説できるレベルまで。3回くらいで完璧になる問題もあれば、10回やってもピンとこない問題もあるの。
地味で、つらい作業になりますが、反復演習が一番効率が良い学習法になります。
どの問題を解くのか?
問題をたくさん解いて、何度も繰り返したらよいというのは理解してもらえたと思います。
では、どの問題をとけばよいのか?
という話になります。
ズバリ言うと、過去問
です。最低でも10年分は必須です。
どの教材で、どのように勉強していくのかは、
独学の人はこちらの記事で詳しく解説しています。
通信受講を検討している人は、各講座で何をどう使うのか具体的なガイダンスが必ずあります。おすすめの通信講座はこちらの記事で紹介しています。
最後にたくさん問題をとけばいいのだからと言って、他資格の問題集に手を出すのはおすすめしません。(一部、一般知識で公務員用の教材を使うことはあります)基本的には行政書士用に作られた問題集をやりこむのが近道です。