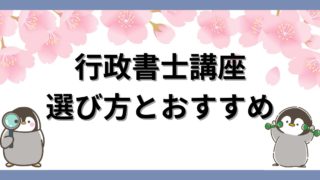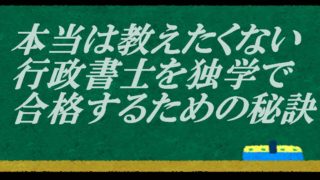行政書士試験本番は11月第2日曜日。
6月からのスタートであれば、準備期間はおよそ5か月。
5か月は微妙な期間。
時間的に万全の準備を整えることは難しいが、合格の可能性が全くないほど短い期間でもない。
5か月程度の短期でも合格圏内に食い込むことは可能。
ただし、誰にでも可能ではない。
人生経験、個人の素養、そして運が影響する。
では、何をどうすればよいのか?
必要最低限を高効率で消化していく。
- 講座受講は必須。
- 取れるところを確実に取る、とらなくていいところはすっぱり捨てる。
6月から始めるのであれば、講座受講は必須
6月からのスタートであれば講座の受講はほぼ必須。
- 効率を購入するのが講座。
スタートが遅いため、高い効率で進めていく必要がある。 - ノウハウや勉強法を模索している時間的余裕はない。
- 独学合格が不可能とは言わないが、絶望的に確率は低くなる。
効率は買う。
私は独学合格者です。
合格後、このブログきっかけで講座を受講させていただきました。
両方の体験で得た結論は講座と独学では、理解までの速度が段違い。
アガルート入門総合カリキュラムを受講しての感想でも話していますが、別世界といっても言い過ぎではない。

そもそも独学は、テキスト読んで、解説見ても、説明や解説の言葉や単語が意味不明なところからのスタートピヨ。
効率を求めるのであれば、講座の力を借りるのが手っ取り早く、間違いが少ない。
ノウハウも同様、特に短期に特化したものを選ぶ
今や多くのノウハウはネットにあふれています。
ただ、短期で、再現性が程度あり、データに基づいたものは極わずか。
ごく少数の実績をもって再現性ありというものもあり、玉石混交の世界。
はっきり言って、自分に合った珠玉のノウハウを多くの石の中から探している時間はありません。
6月から始める場合どの講座を選べばよいのか?おすすめ3選
4ヵ月の短期学習に特化している、資格スクエア森Tの短期集中合格講座
完璧に覚えないと不安なタイプ、フォーサイト ![]()
次年度も意識している人、アガルート入門総合講義/入門総合カリキュラム、または行政書士試験 速習カリキュラム
のセールしているほう
短期学習に特化した資格スクエア
資格スクエア行政書士講座は2022年が初開講ではありますが、担当講師の森Tは伊藤塾で短期講座を担当するなど実績十分です。
文字通り、6・7月から始める人にフィットした講座と言えます。
詳しくは
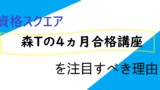
ただ、次年度が本命だと考えている場合は合わない可能性があります。
あくまで短期で走り切る前提。
短期間でも完遂可能なカリキュラムで実績も十分、フォーサイト
人気と実績で安定のフォーサイト ![]() 。
。
おすすめは不合格で全額返金が期待できるバリューパック3。
返金の条件がいくつかありますが、しっかり学習すれば対象になることは難しくありません。
受かっても、不合格でも次につなげることができるのは大きなメリットです。
返金制度![]() の詳細はこちらから ➡フォーサイト返金制度
の詳細はこちらから ➡フォーサイト返金制度 ![]()
次年度も見据えてしっかりとした学習をしたい方向け、アガルート
アガルートは入門総合講義/入門総合カリキュラム、または行政書士試験 速習カリキュラム
のセールしているほうでよいです。
どちらを選んでも十分な学習量になっています。
今年度が次年度どちらに比重を置くかで、今年度なら速習、次年度なら入門でよいと思います。
アガルートの場合、講義の視聴期限がありますが、音声でダウンロードしておくことが可能です。
アガルートに関して詳しくは


ただし、6月後半スタートの場合速習であっても学習量が重い可能性あり。
完全に次年度狙いであれば、すでに次年度対象の入門コースの販売が開始されています。
ただ、年内にすべて教材がそろうわけではありません。
あくまで次年度目標のコース。
講座のノウハウや講師を信じて走り抜けられるかが勝負
4~5か月は行政書士試験においては決して長い期間ではありません。
短期と言えます。
ですが、日常的に学習習慣がない場合、息切れせずに駆け抜けるには長い時間です。
実際に始めてみると、かなりきつい。
また、情報の多い時代ですので様々な情報で迷いが生じることも出てきます。
短期合格を狙うのであれば、迷っている暇はありません。
講座のノウハウや講師を信じて突き進んでいけるかどうかが重要な要素になってきます。
信じてやり切れるかがカギになります。
取るべきところを取り、とらなくていいところはすっぱり捨てる。
短期決戦になるため、フル学習はあきらめたほうが無難です。
行政書士試験は6割で合格の試験ですので、逆に言えば4割切ることができます。
無理にフル学習にこだわれば、どれも中途半端になってしまうリスクがあり、点を積むことが難しくなってきます。
一年かけて勉強している人にとっては後半戦の序盤、同じことをしていても厳しい
10~12か月かけ、1.000~1.200時間を投入するオーソドックスなスタイルの場合、後半戦に入る時期です。
当然の話になりますが、すでに半年進めている人の半分の時間での勝負になります。
専業受験生ならまだしも、社会人であれば時間的に同水準まで追い込むことは事実上不可能。

え?行政書士試験って絶対評価の試験ですよね?他の受験生と競う必要ってあるの?
という疑問を持つ方がいると思いますが、他の記事でも頻繁にお話ししていますが、事実上相対評価の試験だと思ってください。
(令和4年6月現在)、昨年(令和3年試験)の記述がかなり厳しかった、という話は聞いたことあるかもしれません。
これは、前年度の記述以外の得点が全体的なかなり高かった(特に最も配点の大きい行政法がとりやすかった)ために合格者数の調整で採点を厳しくしたと考えるのが自然です。
逆に、全体の記述以外の点が悪い年は記述の採点を甘くして合格者数を増やす場合もあります。
問題全体の難しさのバランスも上げたり下げたりしながら調整をしてくる試験です。
どこを捨てて、どこをやる?
行政書士試験は300点満点中60%の180点が合格点です。
逆にいえば、40%は落としても問題ありません。
では、どこを落としても良いのかといえば、
- 記述の半分(60点満点中30点)
- 一般知識の一部(足切り回避はマスト、あとは運の要素が強い)
- 基礎法学(8点)
- 商法・会社法(20点)
などが想定できますが、基本的には講座の指示に従えば問題ありません。
特に、フォーサイトや資格スクエア森Tの短期集中合格講座はすでに最低限にカスタムされています。
よって、カリキュラムは完璧にすべてこなす必要があります。
5か月程度の期間でもカリキュラムを消化することは十分に可能な分量になっています。
逆に、アガルートであれば、入門総合講義/入門総合カリキュラム、または行政書士試験 速習カリキュラム
のいずれにしても自分でカスタムを入れないと分量的にさばけないはずです。
ただ、苦手を切ることができるのがメリット。
最低限の一般知識対策と、民法・行政法はフルサイズ、
憲法それなりに抑えて、
あとは放置で番号決め打ちでマークして確率で1~2問取れたらいいや
みたいな戦い方もできたりします。
(あくまで6月スタートの話)
どちらが優れているかという話ではなく、タイプの問題です。
少ない分量を完璧にこなすほうが得意な方はフォーサイトや資格スクエア森Tの短期集中合格講座が向いています。
一通り体験してみて、自分で判断して調整したいというのであれば、アガルート行政書士講座が向いています。
来年やろうは、馬鹿野郎
明日やろうは馬鹿野郎
なんていう名言ありますが、行政書士試験でいえば来年受けようと考える人が増えてくるが6月頃からです。
申し込み期限より前に思い立ったなら、その時点がはじめ時です。
6月はまだあきらめるような時期ではありません。
確かに、時間的に厳しく、個人の素養に左右されます。
受かる確率も高くはありません。
ですが、挑むことには意味があります。
十分に当落線上を競えるレベルには届きます。
できなければ、何かしら原因があるはずです。
それがわかるだけでも、次年度でかなり有利な位置で戦うことができます。
一発合格に価値はありません。
思い立った時に即行動でき、最短チャレンジができたことのほうがよほど価値があります。